引越しの費用は、距離や作業内容だけでなく「トラックのサイズ」によっても大きく変わります。
しかし、「自分の荷物量に合うトラックのサイズが分からない」「大きすぎても小さすぎても不安」という方も多いはずです。
ここでは、トラックのサイズと料金の関係、そして選び方のコツをわかりやすく解説します。
【トラックのサイズで変わるもの】
トラックの大きさは、単に「荷物がどれくらい入るか」だけでなく、料金や作業効率にも直結します。大きなトラックを使うほど、次のような点でコストが上がる傾向があります。
- 車両の基本料金:大型トラックはレンタル料・燃料費・保険料が高い
- 人件費:荷物が多いと積み下ろし時間が増え、スタッフの人数も増える
- 走行コスト:車体が大きくなるほど燃費が悪く、高速料金も上がる
- 作業条件:狭い道や住宅街では大型車が入りにくく、手運び作業が必要になる場合もある
このように、トラックのサイズは単純に「大きければ安心」というわけではなく、コストとのバランスが重要です。
トラックサイズ別の特徴と適正
おおまかなトラックの種類と、それぞれに適した引越し規模を見てみましょう。
| トラックの種類 | 積載量の目安 | 向いている人・家庭 |
|---|---|---|
| 軽トラック | 1R・1K程度(荷物少なめ) | 単身で荷物が少ない人、学生の引越し |
| 1トンバン(ハイエースなど) | 1DK程度 | 単身でも家具・家電が多い人 |
| 2トントラック(ショート) | 1LDK〜2DK程度 | 二人暮らしや荷物が多い単身者 |
| 2トントラック(ロング) | 2LDK程度 | 小さな家族の引越しに最適 |
| 4トントラック | 3LDK以上 | 家族4人以上や大型家具・家電が多い家庭 |
| 大型トラック(10トンなど) | 一軒家・オフィス | 長距離移転や荷物量が非常に多い場合 |
トラックを選ぶ際のポイントは、「積み切れるか」「一度で運べるか」「作業環境に適しているか」の3点です。
サイズ別の料金目安
引越し料金は時期や距離によって変動しますが、おおまかな目安は以下の通りです。
- 軽トラック:1〜2万円前後(近距離・荷物少量)
- 1トン車:2〜3万円前後
- 2トン(ショート):2〜4万円前後(市内移動など)
- 2トン(ロング):3.5〜5万円前後(中距離・荷物多め)
- 4トン車:6〜10万円前後(家族・大型家具が多い場合)
また、繁忙期(3〜4月)はこれらの金額が2〜3割高くなることもあります。
【トラック選びで失敗しないためのコツ】
- 荷物量を具体的に把握する
家具・家電・段ボール数をメモしておくと、業者が適切なサイズを提案しやすくなります。 - 台数よりも効率を重視する
2トンを2台使うより、4トン1台にまとめた方が安くなるケースも多いです。 - 搬入環境を確認する
狭い道・坂道・駐車場所が限られている場合は、大型車が入れないことがあります。 - 見積もりを複数取る
業者ごとにトラック区分や料金設定が異なるため、比較することで最適な選択ができます。 - 距離と時間帯にも注目する
長距離移動は大型車で効率よく運んだ方が割安になることがあります。
荷物量を具体的に把握する
トラックのサイズを決めるうえで最も大切なのが、自分の荷物量を正確に把握することです。
見積もりを取るときに「だいたいこのくらい」と答えてしまうと、実際に当日になって「積みきれない」「トラックを追加する必要がある」というトラブルが起こりやすくなります。
以下の手順で、できるだけ正確に把握しておきましょう。
1. 家具・家電の一覧を作る
まず、主要な家具・家電をリスト化します。
たとえば次のようなカテゴリに分けると整理しやすいです。
- 大型家具:ベッド、タンス、本棚、ソファ、食器棚など
- 家電製品:冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レンジ、エアコンなど
- 小型家具・雑貨:テーブル、椅子、照明、カーペット、衣装ケースなど
- 段ボール類:本、衣類、食器、小物、書類などをまとめた箱
この時点で、家具や家電のサイズ(縦・横・高さ)や個数を簡単にメモしておくと、業者が積載量を判断しやすくなります。
2. 段ボールの目安を把握する
段ボールの数は、部屋の広さと荷物の多さでだいたいの目安が決まります。
以下は一般的な目安です。
| 間取り | 段ボールの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 10〜20箱 | 最低限の生活用品のみ |
| 1DK | 20〜30箱 | 家電・衣類が増える |
| 1LDK | 30〜40箱 | 二人暮らしや荷物が多い単身者 |
| 2LDK | 40〜60箱 | 家族2〜3人分 |
| 3LDK以上 | 60箱〜 | 大型家具や季節物も含む |
段ボールの数が増えるほど、トラックのサイズを1ランク上げる必要があるケースが多いです。
3. 部屋ごとに荷物をイメージする
部屋単位で整理すると、見落としを防げます。
- リビング:テレビ台、ソファ、ローテーブル、ラグなど
- キッチン:冷蔵庫、電子レンジ、食器棚、炊飯器など
- 寝室:ベッド、マットレス、クローゼット内の衣類
- 玄関・その他:靴箱、自転車、掃除機、カーテン、観葉植物など
「部屋ごとに書き出す」と、どれくらいのスペースが必要かが見えてきます。
4. 捨てる・譲る荷物を仕分けしておく
引越し前に不要なものを整理しておくと、トラックのサイズを小さくでき、
結果的に料金も安く抑えられます。
- 壊れている・使っていない家電
- 長期間使っていない衣類や雑貨
- 同居先で重複する家具
これらは引越し前にリサイクル・買取・処分しておくのがポイントです。荷物量を減らすことで、トラックサイズを1ランク下げられることもあります。
5. 写真や動画で記録して見積もりに活用する
引越し業者に見積もりを依頼する際、部屋の写真や動画を見せると、より正確なトラックサイズを提案してもらえます。
特にオンライン見積もりや電話見積もりの際には非常に有効です。
6. 家具の寸法をメジャーで測っておく
ソファやベッドなどは「思ったより大きくて入らない」ケースがよくあります。
トラックに積めるかどうかだけでなく、新居の玄関やエレベーターにも通るか確認しておきましょう。
台数よりも効率を重視する
引越し費用を抑えるために、「小さなトラックを2台に分ければ安く済むのでは?」と考える人は多いですが、
実際にはトラックの台数を増やすより、1台にまとめた方が効率がよく、費用も抑えられるケースが多いです。
その理由と、効率的な選び方のコツを詳しく解説します。
1. トラックの台数が増えると費用も倍増する
引越し料金は「車両の台数 × 作業員の人数 × 移動距離」で計算されるのが一般的です。
したがって、トラックを増やせば単純にその分の人件費・車両費が追加されます。
例を挙げると:
- 2トントラックを2台使用した場合
→ ドライバー2人、作業員もそれぞれ配置されるため、人件費・燃料費が倍近くになる - 4トントラック1台にまとめた場合
→ ドライバー1人で済み、作業効率も向上する
結果として、2台よりも1台の方が約20〜40%安くなることも珍しくありません。
2. 作業時間と段取りがシンプルになる
トラックが複数あると、次のような非効率が発生しやすくなります。
- 積み込み・積み下ろしの順序を分担する必要がある
- どの荷物をどちらのトラックに積むかを現場で調整する手間がかかる
- 現地到着時間がずれると、作業待ちの時間が発生する
一方で、1台のトラックにまとめれば、作業の流れが一方向でスムーズ。
引越し全体の時間が短くなり、スタッフの稼働時間も減るため、結果的にコスト削減につながります。
3. 複数台は燃料・高速代も倍増
トラック1台ごとに燃料や高速料金が発生します。
例えば、片道100kmの引越しを2台で行えば、ガソリン代・高速代が単純に2倍になります。
長距離引越しではこの差が特に大きく、1台で済ませた方が1〜2万円以上安くなることもあります。
4. ただし「環境に合わせた例外」もある
効率重視といっても、すべてのケースで大型1台が最適というわけではありません。
次のような場合は、むしろ小型車を2台に分けた方が現実的です。
- 住宅前の道路が狭く、4トン車が入れない
- マンションの搬入口に高さ制限がある
- 搬出と搬入の距離が離れ、同時並行で作業したい
このような場合は、作業環境に合わせて台数を分けることが結果的に効率的になります。
5. 業者による積載効率の違いも考慮する
同じ「2トントラック」でも、業者によって積載量が異なることがあります。荷台の高さ・奥行き・形状、さらには積み方の工夫によっても入る量は変わります。
したがって、複数の業者で同じ荷物量を伝えて見積もりを比較することが大切です。A社では「2トン×2台」と言われても、B社では「4トン1台で十分」となることもあります。
【効率を最大化するためのポイント】
- 荷物を事前にまとめ、「すぐ積める状態」にしておく
- 大型家具を先に積み込む計画を立てる(積載スペースを最適化)
- 荷物の配置を写真や図で示すと、業者が効率よく積み込める
- 搬出先と搬入先の道路状況を事前に確認しておく
こうした事前準備をすることで、1台で積み切る確率が高まり、結果的にコスト削減にもつながります。
ある家族の引越し(3LDK → 3LDK)では、最初の見積もりで「2トン車×2台=約25万円」でした。
しかし、他社で4トントラック1台にまとめたところ、約14万円で済んだという例があります。
このように、「台数を減らして効率を上げる」だけで、10万円以上の差が出ることもあるのです。
搬入環境を確認する
引越しの見積もりで見落とされがちなのが、「搬入・搬出環境」の確認です。
同じ荷物量でも、建物の構造や周辺環境によって、必要な人員・時間・トラックのサイズが大きく変わります。
搬入環境を正しく把握しておくことで、「当日トラックが入れない」「階段搬入で追加料金が発生した」といったトラブルを防げます。ここでは、その具体的な確認ポイントを詳しく説明します。
1. トラックが停められる場所を確認する
まずは、トラックが駐車・停車できるスペースがあるかどうかをチェックします。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 建物前に一時的にトラックを停められる場所があるか
- 道幅が狭く、大型トラックが入れない道路ではないか
- 駐車禁止区域や時間帯制限があるか
- 集合住宅の場合、搬入専用スペースが予約制になっていないか
もしトラックが建物前に止められない場合、手運び距離(トラックから玄関までの距離)が長くなり、追加料金が発生することがあります。
2. 道路の幅・高さ制限を確認する
特に都市部や住宅密集地では、「4トントラックが入れない」「坂道で車両が止めづらい」といったケースがよくあります。
確認すべき項目:
- 道幅(大型トラックが通れる幅は最低3m以上が理想)
- 電線・樹木・看板などの高さ制限(車高制限3.3m程度を目安に)
- 急坂・カーブの有無(特に地方や山間部では注意)
もし4トントラックが入れない場合は、2トントラックに分けるか、台車で手運びする必要があります。その場合、作業時間が増えて費用が上がることもあります。
3. 建物の構造をチェックする
建物の構造も、引越し作業の難易度に直結します。
見積もり時に必ず以下を伝えるようにしましょう。
- 階数とエレベーターの有無
→ エレベーターがない3階以上の建物は「階段搬入」となり、追加料金が発生する場合があります。 - エレベーターのサイズ
→ ソファや冷蔵庫などの大型家具が入らないと、階段での搬入が必要になります。 - 共用スペースの幅・高さ
→ 廊下やドアの幅が狭いと、分解作業が必要になることもあります。
特にマンションやアパートでは、管理規約で「引越し可能な時間帯」「養生(床保護)義務」などが決まっていることもあるため、事前確認を忘れずに。
4. 新居の搬入動線を確認する
搬入時は「トラック → 玄関 → 各部屋」までの動線がスムーズかどうかが大切です。
- エントランスから部屋までの距離
- 廊下の幅・角の曲がりやすさ
- 階段の幅や手すりの位置
- 玄関の間口サイズ
ソファやベッドなどの大型家具が玄関や廊下を通らない場合、「吊り上げ搬入」や「分解・再組み立て」などの特別作業が必要となります。このような作業は、数千〜数万円の追加料金になることもあります。
5. 搬入・搬出の時間帯も確認する
マンションやオフィスビルなどでは、
引越し作業ができる時間帯が制限されていることがあります。
- 平日〇時〜〇時まで
- 土日・祝日は不可
- 管理人立ち会いが必要
この制限を見落とすと、当日トラックが到着しても作業できず、
「再訪費用」や「保管料」が発生してしまうこともあります。
【搬入環境を確認するメリット】
搬入環境をきちんと伝えておくことで、次のようなメリットが得られます。
- 最適なトラックサイズを選びやすくなる
- 当日の作業がスムーズに進み、時間短縮になる
- 追加料金やトラブルのリスクを防げる
- 必要な人員・資材を事前に準備してもらえる
つまり、「搬入環境の確認」はコストと安全の両面で最も重要な要素なのです。
【事前に写真や動画を送るのもおすすめ】
最近は、オンライン見積もりやLINE見積もりが一般的になっています。現地調査が難しい場合は、建物の外観・駐車スペース・エレベーター内部などの写真を送ると、業者が的確に判断でき、無駄な費用を防げます。
見積もりを複数取る
引越し費用を抑えるために、最も効果的な方法の一つが「複数の業者から見積もりを取る」ことです。
同じ荷物・同じ距離でも、業者によって料金差が2倍以上になることもあります。
なぜここまで違うのか、そしてどうやって上手に見積もりを取るかを詳しく解説します。
1. 業者によって料金の基準が違う
引越し業者はそれぞれ独自の料金体系を持っています。
そのため、同じ条件でも見積もり金額が大きく異なることがあります。
主な違いは以下の通りです。
- 車両サイズの考え方が異なる
→ ある業者では2トン車で十分と言われても、別の業者では4トンを勧められることもある。 - 作業員の人数設定が違う
→ 人員を多く配置する業者ほど、作業は早いが費用は高くなる。 - サービス内容に差がある
→ 梱包材無料・エアコン脱着込みなど、付帯サービスの範囲が違う。 - 時期・時間帯での料金変動
→ 同じ日でも、午前便と午後便で金額が違う業者も多い。
「基本料金+作業条件+サービス内容」の組み合わせで、業者ごとの見積もりは大きく変わります。
2. 一括見積もりサイトを活用する
複数の業者に一つずつ連絡するのは手間がかかります。そこで便利なのが、一括見積もりサービスの利用です。
一度情報を入力すれば、複数の業者から見積もりを受け取ることができ、価格やサービス内容を簡単に比較できます。
利用時のコツ:
- 荷物量・部屋の間取り・引越し希望日を正確に入力する
- 「電話ではなくメール希望」と指定すれば、営業電話を減らせる
- 最低でも3〜5社の見積もりを比較する
ただし、安さだけで選ばず、口コミや対応の丁寧さもチェックしましょう。
3. 相見積もりを取ることで価格交渉がしやすくなる
複数の見積もりを取る最大のメリットは、価格交渉の材料になることです。
たとえば、次のように伝えると効果的です。
「他社では○万円だったのですが、御社で同条件ならどれくらいになりますか?」
業者は他社の価格を意識しているため、「それならうちは1万円安くします」といった調整をしてくれることもあります。
特に、繁忙期を避けた平日・午後便・中距離引越しでは、交渉が通りやすい傾向があります。
4. 見積もりの比較ポイント
単純に金額だけを見るのではなく、次の項目もチェックしましょう。
- トラックのサイズ・台数
- 作業員の人数
- 梱包資材の有無(ダンボール・ガムテープなど)
- 家電の取り外し・設置費用が含まれているか
- 保険・補償内容(破損時の対応)
- キャンセル料・日程変更の条件
これらを比較すれば、「安いけれど手抜きな業者」を避けられます。
【訪問見積もりを受ける場合の注意点】
荷物量が多い場合は、業者が自宅に来て行う「訪問見積もり」を勧められます。
このときのポイントは以下の通りです。
- 荷物を隠さず、実際の量を正直に見せる
- 不要品を処分する予定があれば、その旨を事前に伝える
- 当日追加料金が出ないよう、細かく質問する
- 他社の見積もりをちらっと見せると、値下げ交渉の材料になる
訪問見積もりは手間に感じるかもしれませんが、
その分、料金の正確さが増し、当日トラブルが減るという大きな利点があります。
【複数見積もりで失敗しないためのポイント】
- 見積もり内容を必ず書面またはメールで残す
- あまりに安すぎる業者は、後から追加請求される可能性がある
- 即決を迫る業者には注意(他社比較を待たせないための手口の場合あり)
- 同じ条件(日時・荷物量)で比較する
これらを徹底することで、
価格だけでなく「信頼できる業者」を選ぶことができます。
5. 結果として「最大で数万円の差」が出ることも
実際のデータでは、同じ条件の引越しでも最安と最高で10万円以上の差が出ることもあります。
特に単身引越しでは3〜5万円、家族引越しでは5〜15万円ほど変わるケースも珍しくありません。
複数見積もりを取るだけで、その中の“コスパ最強業者”を選べるのは大きなメリットです。
距離と時間帯にも注目する
引越し料金を左右する大きな要素のひとつが、「距離」と「時間帯」です。
同じ荷物量・同じトラックサイズでも、走行距離や作業の時間帯によって料金が数万円変わることがあります。
ここでは、なぜ距離と時間帯が料金に影響するのか、そしてどのようにすれば費用を抑えられるのかを詳しく解説します。
1. 引越し料金は「距離 × 時間 × 作業内容」で決まる
引越し業者の料金は、主に以下の3つの要素で構成されています。
- 走行距離:トラックの移動距離(ガソリン代・高速料金・ドライバーの稼働時間など)
- 作業時間:積み込みから搬入完了までの作業にかかる時間
- 人件費:スタッフの人数と拘束時間
つまり、「距離が長い」「時間がかかる」「作業が込み合う時間帯」の条件が重なると、
料金は一気に上がる仕組みです。
2. 距離による料金の目安
一般的な引越し業界の距離別料金の相場は、次のようになります。
| 距離の目安 | 単身(1R〜1DK) | 家族(2LDK〜3LDK) |
|---|---|---|
| ~15km(市内) | 約2万〜4万円 | 約4万〜8万円 |
| ~50km(近隣県) | 約3万〜5万円 | 約6万〜10万円 |
| ~200km(中距離) | 約4万〜8万円 | 約8万〜15万円 |
| 200km以上(長距離) | 約6万〜10万円 | 約12万〜25万円以上 |
時期やトラックサイズによって変動あり。繁忙期はこれより20〜50%高くなることも。距離が伸びるほど「燃料費・高速料金・運転手の拘束時間」が増えるため、料金に直接反映されます。
3. 時間帯によって料金が変わる理由
多くの業者では、時間帯別に料金設定を行っています。
同じ日でも「午前」「午後」「夜間」で金額が異なる場合があります。
| 時間帯 | 特徴 | 料金傾向 |
|---|---|---|
| 午前便 | 人気が高く、作業がスムーズ | やや高め(需要が集中) |
| 午後便 | 午前便の作業後になるため、時間が読みにくい | 割安になることが多い |
| 夜間便・フリー便 | 作業開始時間が指定できない | 最も安くなる傾向 |
特に「時間指定なし(フリー便)」は、業者がスケジュールに合わせて動けるため、料金を下げやすいプランです。
もしスケジュールに余裕があるなら、午後便やフリー便を選ぶだけで1〜3万円安くなることもあります。
4. 距離と時間帯の組み合わせでコスパが変わる
距離と時間帯は、それぞれが料金に影響しますが、この2つの組み合わせによってさらにコストが変動します。
- 市内引越し × 午前便 → 需要が高く、割高
- 市内引越し × フリー便 → 短距離なので、午後便でも十分対応可能で安い
- 中距離引越し × 午前便 → 移動時間が必要なので、午前出発が一般的(標準価格)
- 長距離引越し × 夜間出発 → 翌日着にしてスケジュール調整すると割安になる
業者によっては「夜積み・翌朝届け」という形で効率化している場合もあります。
5. 渋滞・交通事情も見積もりに影響する
特に都市部では、渋滞や交通規制によって作業時間が延びるリスクがあります。
このため、業者は見積もり時に「作業時間を余裕を持って設定」します。
- 午前8〜10時:通勤渋滞で到着が遅れる可能性
- 夕方16〜18時:帰宅ラッシュで搬入が遅れる
- 土日祝日:一般車両の増加で交通が混む
こうした時間帯を避けて予約すれば、同じ距離でも料金が下がるケースがあります。
【距離と時間帯をうまく調整するコツ】
- 近距離なら午後便やフリー便を選ぶ
→ 時間指定にこだわらなければ数千円〜1万円節約可能。 - 中・長距離の場合は翌日着にする
→ 1泊の保管を挟むよりも、夜間運搬で翌朝着にした方が安く済むことがある。 - 交通の混雑しない日・時間を狙う
→ 平日の昼間、または火曜〜木曜が最も空いており、料金も安定。 - 引越し先の交通環境も考慮する
→ 駅前や繁華街など、搬入に時間がかかる場所は割高になりやすい。
ある単身引越し(東京都内15km以内)の場合:
- 午前便指定 → 38,000円
- 午後フリー便 → 29,000円
同じ条件で約9,000円の差が出ました。
家族引越しなど規模が大きい場合は、午前・午後の違いだけで2万円以上の差になることもあります。
【距離・時間帯を考慮することで得られるメリット】
- 無駄なコストを抑えられる
- スケジュールが柔軟になり、予約が取りやすい
- 渋滞や混雑による遅延リスクを減らせる
- 引越し当日のストレスを軽減できる
つまり、「距離と時間帯に注目する」ことで、料金・効率・安全性のすべてを最適化できるのです。
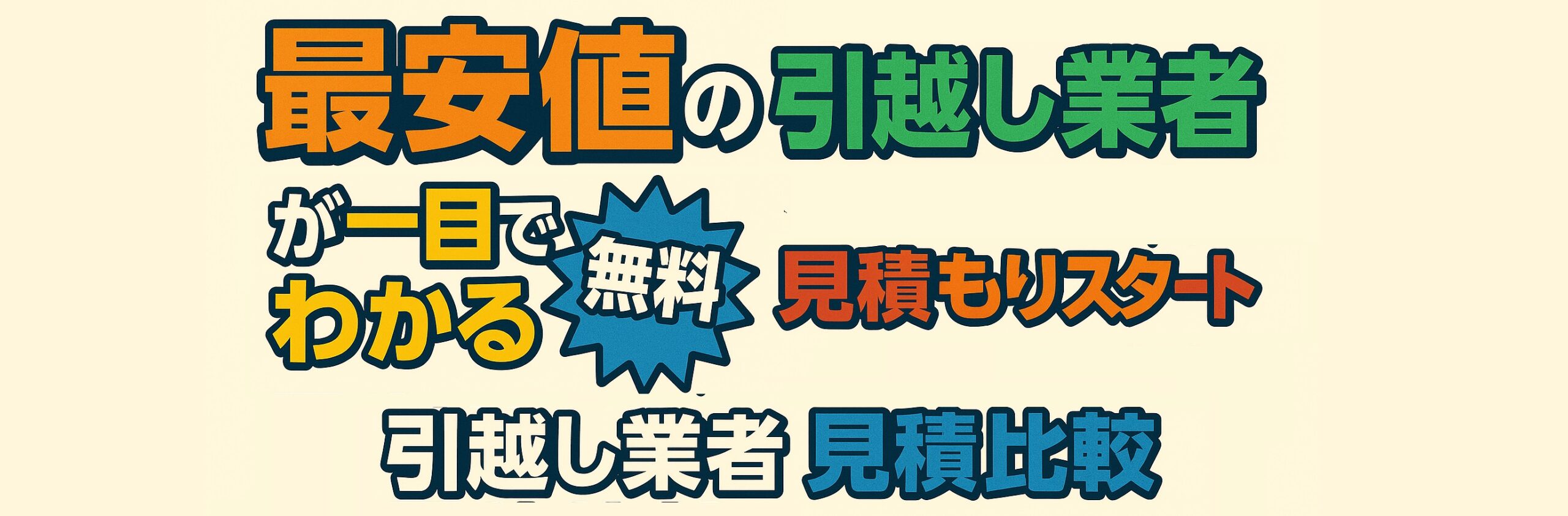
|

