引越しは新しい生活のスタートを切る大切なイベントですが、当日になって「思ったより時間がかかった」「予定通りに終わらなかった」といったトラブルも少なくありません。
引越しにかかる時間は、荷物の量や移動距離、作業する人数によって大きく変わります。ここでは、それぞれの条件別に引越しにかかる時間の目安を詳しく比較していきます。
作業量(荷物の量・部屋の広さ)で見る時間の目安
引越し作業時間の基本となるのが、荷物の量です。一般的には部屋の間取りが広くなるほど、作業時間も長くなります。
| 間取り | 荷物量の目安 | 作業時間(積み込み~搬入まで) |
|---|---|---|
| 1R・1K | 一人暮らし・荷物少なめ | 約2〜3時間 |
| 1DK・1LDK | 一人暮らし・荷物多め/二人暮らし | 約3〜5時間 |
| 2DK・2LDK | カップル・小さな家族 | 約4〜6時間 |
| 3LDK以上 | ファミリー・荷物多め | 約6〜9時間以上 |
- 梱包や開梱作業を含める場合は、上記時間にプラス1〜3時間を見込む
- 家具の分解・組み立てがある場合はさらに時間がかかる
距離による違い(移動距離・地域間での差)
引越しは距離によっても大きく所要時間が変わります。特に長距離引越しでは日をまたぐケースもあります。
| 距離区分 | 距離の目安 | 移動時間の目安 |
|---|---|---|
| 近距離(同一市区内) | ~30km | 約30分〜1時間 |
| 中距離(県内・隣県) | 30〜100km | 約1〜2時間 |
| 長距離(県外・地方間) | 100km以上 | 約3時間〜1日 |
【注意点】
- 長距離引越しでは「荷物運搬日」と「搬入日」が別になることが多い
- 交通渋滞や天候によっても所要時間が変動する
作業人数による違い(作業効率・家族構成別)
作業にあたる人数も、引越し時間に大きな影響を与えます。
少人数では時間がかかりやすく、多人数だと効率的に進められます。
| 作業人数 | 対応するケース | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 1人 | 単身・荷物少なめ | 約2〜3時間 |
| 2人 | 一人暮らし・カップル | 約3〜4時間 |
| 3〜4人 | ファミリー・中型物件 | 約4〜6時間 |
| 5人以上 | 大型住宅・荷物多め | 約6〜9時間以上 |
- 作業員が多いほどスムーズだが、トラックの積み込みや配置の調整に時間がかかる場合もある
- 家族構成が多いと、家具・家電・衣類などの荷物が増えるため作業時間が長くなる傾向がある
引越し前後に必要な準備時間
当日の作業だけでなく、事前準備や引越し後の整理にも時間がかかります。全体のスケジュールを立てる際は、以下も考慮することが重要です。
| 工程 | 内容 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 梱包 | 荷物をまとめる作業 | 2〜5日(自分で行う場合) |
| 開梱 | 新居で荷物を出す | 半日〜2日 |
| 手続き関係 | 電気・ガス・水道・住所変更など | 約1日 |
補足
- 梱包に時間がかかるため、早めに準備を始めることがポイント
- 引越し業者の「梱包サービス」を利用すると、作業を大幅に短縮できる
引越しタイプ別の総所要時間の目安
| 引越しタイプ | 総所要時間(目安) |
|---|---|
| 単身(近距離) | 約3〜5時間 |
| カップル(中距離) | 約5〜7時間 |
| ファミリー(近距離) | 約6〜9時間 |
| ファミリー(長距離) | 1〜2日(場合によっては3日) |
【スムーズに引越しを進めるためのポイント】
- 午前便を選ぶと作業が早く終わりやすい
- 家具や家電の配置を事前に決めておく
- エレベーターの有無やトラックの駐車場所を確認しておく
- 荷造りは前日までに完了させておく
目次
午前便を選ぶと作業が早く終わりやすい
引越しの際、業者に依頼するときに「午前便」「午後便」「フリー便」などの時間帯を選ぶことができます。
中でも、午前便は作業がスムーズに進みやすく、結果的に一日を有効に使えるというメリットがあります。
ここでは、午前便を選ぶことで引越しが早く終わる理由と、その際に注意すべきポイントを詳しく解説します。
午前便が早く終わる主な理由
午前便の最大の利点は、「作業の開始が早い」ことです。以下のような要素が、作業時間の短縮につながります。
1. 早朝から作業を開始できる
- 午前便は、一般的に8時〜10時頃から作業が始まります。
- 早い時間帯に作業をスタートできるため、昼過ぎには荷物の搬出・搬入が完了するケースが多いです。
- 午後の時間を片付けや新居の整理に使えるため、スケジュールに余裕が生まれます。
2. 交通渋滞の影響を受けにくい
- 朝の時間帯はまだ交通量が少なく、移動がスムーズに進む傾向があります。
- 午後や夕方になると渋滞が発生しやすく、搬入に時間がかかる場合もあります。
- 特に都市部では、午前便の方が予定通りに作業を終えやすいです。
3. 業者のスケジュールが安定している
- 午前便はその日の最初の作業であるため、予定通りに開始できる確率が高いです。
- 午後便は、午前中の引越しが長引いた場合に開始時間が遅れることもあります。
- 時間に正確で、全体の流れが計画通りに進みやすいのが特徴です。
【午前便を選ぶ際の注意点】
午前便は非常に人気がありますが、いくつかの注意点もあります。
予約や準備の段階で次の点を押さえておきましょう。
1. 人気が高く、予約が早く埋まりやすい
- 午前便は需要が高く、特に土日や月末などの繁忙期にはすぐに予約が埋まります。
- 少なくとも1〜2週間前には見積もりを取り、早めに予約することが大切です。
2. 料金がやや高めになる傾向がある
- 同じ条件でも、午後便やフリー便に比べて午前便の方が料金が高く設定されている場合があります。
- ただし、「作業の正確さ」「時間の効率」「安心感」を考えれば、コストパフォーマンスは高いといえます。
3. 朝の準備を万全にしておく必要がある
- 当日朝から作業が始まるため、前日までに荷造りを完全に終えておくことが重要です。
- 駐車スペースやエレベーターの使用可能時間も事前に確認しておくと安心です。
- 朝の作業開始に遅れると、全体のスケジュールがずれ込む原因になるため注意しましょう。
【午前便がおすすめの人】
午前便は、以下のような人に特に向いています。
- その日のうちに新居の整理を終わらせたい人
- 小さな子どもやペットがいて、落ち着いて引越しを済ませたい人
- 仕事や予定の都合で午後を自由に使いたい人
- 渋滞や時間遅延のリスクを減らしたい人
家具や家電の配置を事前に決めておく
引越し当日は、荷物の搬入・設置・片付けと、何かと慌ただしいものです。特に家具や家電の配置が決まっていないと、どこに置くかをその場で考えることになり、作業が滞る原因になります。
事前に配置を決めておくことで、引越し作業を効率化できるだけでなく、新居での生活をスムーズにスタートさせることができます。
家具や家電の配置を事前に決めるメリット
1. 搬入がスムーズに進む
- 配置場所が決まっていれば、引越し業者が迷わず設置できます。
- 現場で「この棚はどこに置きますか?」という確認が減り、作業が中断しにくくなります。
- 大型家具や家電の動線を確保しておくことで、狭い通路でのトラブル(壁や床の傷など)も防げます。
2. 無駄な移動や再設置がなくなる
- 事前にレイアウトを決めておかないと、後から「やっぱりこっちにしよう」と再配置する手間が発生します。
- 家具の再移動は大きな労力が必要で、傷や破損のリスクも増えます。
- 初めから最適な場所に置けるようにしておくことで、効率的に作業が進みます。
3. 配線やコンセント位置を把握できる
- 冷蔵庫や洗濯機などの家電は、コンセントや水道口の位置に合わせて配置する必要があります。
- 引越し前に新居の間取り図を確認し、電源や配線の位置を把握しておくと、スムーズに設置できます。
- 延長コードや分配タップが必要な場合も、事前に準備しておけます。
4. インテリアや生活動線を整えやすい
- 家具の位置は、生活の快適さを左右します。
- ソファやテレビの距離、ダイニングテーブルの動線、ベッドと窓の位置などを事前に検討しておくことで、住みやすい空間を作りやすくなります。
- 実際に新居の図面を使って「家具レイアウト図」を作っておくと、当日も分かりやすく指示できます。
効果的な配置決めのポイント
- 新居の間取り図を用意する
不動産会社からもらえる間取り図を活用し、家具や家電のサイズを書き込むとイメージがしやすくなります。 - 家具・家電の寸法を正確に測る
ソファ、冷蔵庫、洗濯機、ベッドなどの大きさを測定し、設置予定場所に入るかを確認します。
特に「搬入口(ドアや廊下の幅)」は忘れずにチェックしましょう。 - コンセント・窓・ドアの位置を確認する
家電は電源位置によって設置場所が制限される場合があります。
また、家具が窓やドアの開閉を妨げないように配置を工夫します。 - 紙やアプリでレイアウトを可視化する
- 方眼紙に間取りを描いて配置を検討する
- 家具配置アプリや不動産サイトのシミュレーターを使う
こうしたツールを使うと、当日の指示が具体的にできます。
- 業者用に「配置メモ」を用意する
家具ごとに「リビング右側」「寝室奥」などのメモを貼っておくと、作業員が迷わず設置できます。
大型家具は壁や床を傷つけにくいよう、置き場所に保護マットを準備しておくと安心です。
家具配置を事前に決めておくべきタイミング
- 新居の鍵を受け取った直後:現地で寸法を測り、間取りを確認する
- 引越しの1週間前まで:家具・家電の配置を決定し、図面に反映させる
- 引越し前日まで:家具に配置番号やラベルを貼り、搬入時に指示できるよう準備する
【注意点】
- 大型家具を壁際にぴったり設置すると、コンセントが隠れて使いづらくなることがあります。
- 冷蔵庫や洗濯機は通気スペースや配線スペースを考慮して、余裕を持たせることが大切です。
- 窓際に家電を置くと直射日光や湿気の影響を受ける場合があるため、配置場所には注意が必要です。
エレベーターの有無やトラックの駐車場所を確認しておく
引越し作業をスムーズに進めるためには、事前準備が欠かせません。その中でも意外と見落とされがちなのが、「エレベーターの有無」と「トラックの駐車場所の確保」です。
これらの確認を怠ると、当日になって作業が遅れたり、追加料金が発生したりすることもあります。ここでは、引越し前に確認しておくべきポイントと、その対策を詳しく解説します。
エレベーターの有無を確認しておく理由
1. 作業時間に大きく影響する
- エレベーターがあるかどうかで、荷物の搬出・搬入スピードが大きく変わります。
- 例えば、同じ荷物量でも「3階エレベーターなし」の場合、エレベーター付きの建物に比べて30〜50%程度時間が多くかかることもあります。
- 引越し業者もエレベーターの有無をもとに作業人員やトラックの台数を決めるため、正確な情報が必要です。
2. 追加料金が発生する場合がある
- エレベーターがない建物では、「階段作業料」や「人力運搬料」が加算されることがあります。
- 特に3階以上の階段作業になると、1人暮らしでも数千円、ファミリー層では1万円以上の追加になることもあります。
- 見積もり時に「エレベーターなし」と伝えておくことで、当日のトラブルを防げます。
3. 荷物のサイズ制限を確認できる
- エレベーターがあっても、家具や家電が入らないケースがあります。
- 特に冷蔵庫やベッドなどの大型家具は、エレベーターの「ドア幅」や「奥行き」を確認しておきましょう。
- 搬入が不可能な場合は、クレーン作業や分解作業が必要になる場合もあります。
駐車場所を確認しておく理由
1. 作業時間と安全性に関わる
- トラックを建物の近くに停められない場合、荷物の運搬距離が長くなり、作業時間が増えます。
- 駐車位置が遠いと、荷物の落下や破損のリスクも高まります。
- トラックを建物の入口付近やエレベーター近くに停められるかを確認しておきましょう。
2. 駐車許可が必要な場合がある
- マンションや商業施設では、「敷地内駐車には管理会社の許可」が必要な場合があります。
- 管理人室や管理組合に事前に相談し、引越し当日の駐車場所・時間帯・ルールを確認しておくと安心です。
- 道路に面した住宅では、一時的な路上駐車に警察の道路使用許可が必要なこともあります。
【トラックのサイズに注意】
- 大型トラック(2トン以上)は、住宅地やマンションの敷地に入れない場合があります。
- 道幅・高さ制限・カーブの有無などを確認しておき、必要に応じて小型トラックへの変更を業者に依頼しましょう。
- 駐車スペースが狭い場合は、近隣のコインパーキングの場所を事前に調べておくとスムーズです。
事前確認のチェックリスト
引越し業者への見積もり依頼時に、以下の項目を確認しておくと安心です。
エレベーター関連
- エレベーターの有無(あり/なし)
- 積載可能サイズ(高さ・幅・奥行き)
- 搬入口から部屋までの距離
- 搬入時間の制限(夜間不可・日曜不可など)
駐車場所関連
- 建物敷地内にトラックが駐車できるか
- 駐車許可が必要か(管理会社や警察に要確認)
- 駐車位置から玄関までの距離・段差
- 当日混雑が予想される時間帯の確認
【確認しておくと良いタイミング】
- 引越しの1〜2週間前:現地でエレベーターや駐車スペースを下見
- 見積もり前:業者に正確な情報を伝える
- 前日まで:管理会社や近隣住民に連絡し、駐車の可否を再確認
【注意点】
- エレベーター使用時は、住人が利用する時間帯を避けるように配慮する
- 共用部分(廊下・エントランス)を養生してもらうよう業者に依頼する
- 駐車場所が離れている場合は、カートや台車を準備しておくと効率的
荷造りは前日までに完了させておく
引越し当日は、荷物の搬出・搬入・掃除・手続きなど、想像以上に多くの作業があります。
その中で「荷造りが終わっていない」という状況になると、作業が大幅に遅れ、引越し業者や自分自身にも負担がかかってしまいます。
スムーズに引越しを進めるためには、荷造りは前日までに完了させておくことが鉄則です。ここでは、その理由と具体的な準備方法を紹介します。
荷造りを前日までに終わらせておくべき理由
1. 当日の作業をスムーズに進められる
- 荷造りが終わっていれば、当日は業者がすぐに作業を開始できます。
- 段ボールがまだ開いていたり、家具の中身が残っていたりすると、作業が一時停止し、全体のスケジュールが遅れます。
- 特に午前便を選んでいる場合、朝のスタート時間がずれるとその後の流れにも影響します。
2. 荷物の破損や紛失を防げる
- 慌てて荷造りをすると、緩衝材を入れ忘れたり、箱詰めが不十分になったりしがちです。
- 前日までに落ち着いて梱包を済ませておけば、荷物を丁寧に保護でき、安全に運搬できます。
- 「何がどこに入っているか」を把握できるため、引越し後の開梱もスムーズになります。
3. 当日の精神的な余裕が生まれる
- 引越し当日は、鍵の受け渡しや電気・ガスの立ち会いなど、荷造り以外のタスクも多くあります。
- 荷造りが完了していれば、当日は搬出と新居での受け入れに集中できます。
- 急なトラブルにも落ち着いて対応できるようになります。
4. 不用品を整理する時間が確保できる
- 荷造りを早めに進めることで、「持っていくもの」「処分するもの」を整理する時間が取れます。
- 不用品を減らすことで、引越し費用を抑えることも可能です。
- リサイクルや粗大ゴミ回収の手配にも余裕が生まれます。
効率的に荷造りを進めるためのステップ
ステップ1:荷物を分類する
- 「すぐ使うもの」「使わないもの」「捨てるもの」の3つに分ける。
- 季節外の衣類や普段使わない食器など、早めに梱包して問題ないものから始める。
- 荷造りの初期段階では、生活に必要な最低限のものを残しておく。
ステップ2:部屋ごとに進める
- 「キッチン → 寝室 → リビング → 洗面所」のように、エリアごとに荷造りを完了させていく。
- 段ボールには「部屋名」を書いておくと、搬入時に業者が迷わず運べる。
- 重いもの(本など)は小さい箱に、軽いもの(衣類など)は大きい箱に分けると安全。
ステップ3:ラベルを活用する
- 段ボールに「中身」「行き先(部屋名)」「取扱注意(割れ物・上積厳禁など)」を記載する。
- 同じような箱が多い場合は、色付きのテープやマーカーを使って区別すると便利。
- 「すぐ使うもの」には「★マーク」などをつけておくと、開梱時に探しやすい。
ステップ4:前日までにすべての箱詰めを完了する
- 引越し前日は、生活に最低限必要なもの(歯ブラシ・タオル・着替え・充電器など)を残す程度にする。
- それ以外の荷物はすべて段ボールにまとめ、すぐに運べる状態にしておく。
- 家具の中(引き出し・クローゼット)も空にし、扉や引き出しをテープで固定しておく。
前日にしておく最終チェック項目
- すべての段ボールにラベルが貼られているか
- 割れ物・精密機器がしっかり保護されているか
- 家具や家電の中身が空になっているか
- 冷蔵庫の中身を処分・清掃し、電源を抜いたか
- 洗濯機の排水ホースを外し、水抜きを行ったか
- 玄関や廊下に荷物をまとめ、搬出しやすい状態にしてあるか
【荷造りを前日までに完了させるためのコツ】
- 1週間前から少しずつ始める:1日1〜2時間でも進めておくと、前日の負担が軽くなる。
- 引越し当日に使うものだけを別袋にまとめる:洗面用具・充電器・貴重品などを一つのバッグに入れておく。
- プロの梱包サービスを検討する:忙しい人や荷物が多い人は、引越し業者の「荷造り代行サービス」を利用するのも効果的。
【注意点】
- 前日に荷造りが終わっていないと、作業が遅れたり、追加料金を請求される場合がある。
- 荷物の梱包を業者に任せる場合でも、「どの荷物を運ぶか」「不要なものはどれか」を明確にしておく。
- 荷造り途中で出たゴミは、前日までに処分を済ませるのが理想。
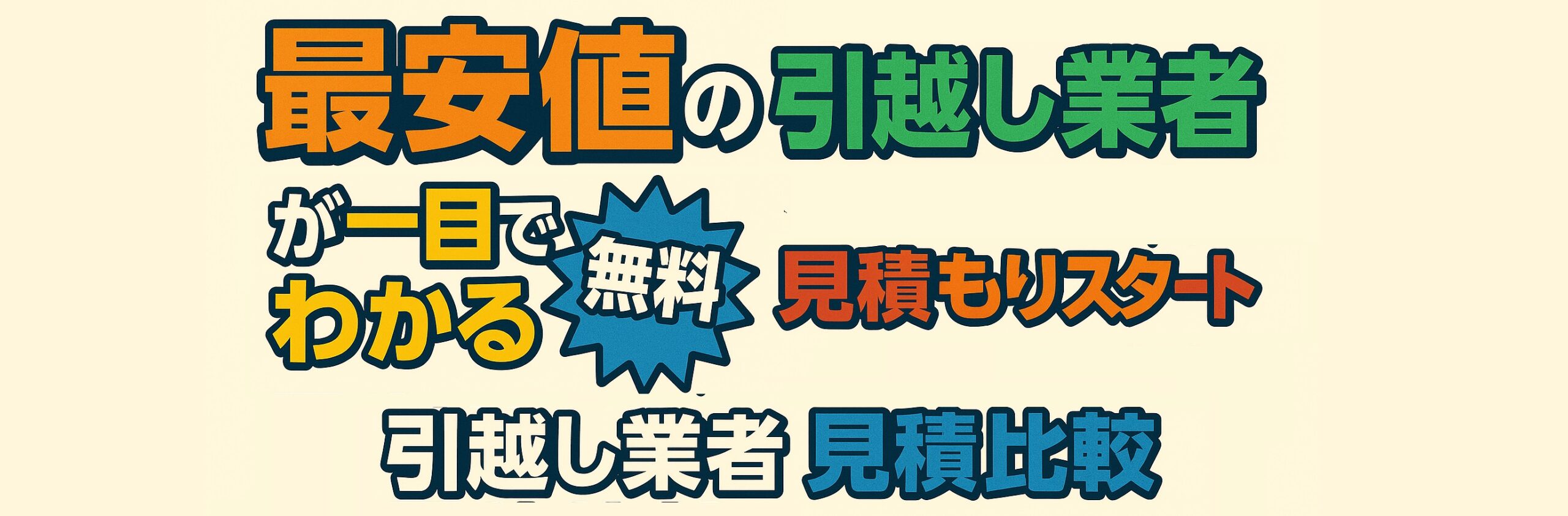
|

