引越しは新生活のスタートとして楽しみな一方で、思った以上に費用がかかるものです。特に、引越しシーズンや業者選びを誤ると、数万円単位で料金が変わることも珍しくありません。
そこで今回は、引越し料金をできるだけ安く抑えるための具体的な10のコツを紹介します。ちょっとした工夫で費用を大幅に節約することができます。
目次
複数の業者に相見積もりを取る
引越し料金を安く抑えたいなら、最初にやるべきことが「相見積もり(複数社の見積もり比較)」です。
引越し業界には明確な「定価」がなく、同じ条件でも業者によって料金差が2倍以上になることもあります。
つまり、相見積もりを取るだけで数万円単位の節約ができる可能性があります。
相見積もりを取る際の基本ステップ
1. 引越しの条件を明確にする
見積もりを依頼する前に、以下の項目を整理しておくとスムーズです。
- 引越し希望日(第1〜第3候補を用意)
- 現在と新居の住所
- 荷物の量(家具・家電・段ボール数など)
- エレベーターの有無
- 梱包を自分で行うかどうか
同じ条件を提示することで、業者間の見積もりを正確に比較できます。
2. 3〜5社に見積もりを依頼する
1社だけでは「相場」が分かりません。最低でも3〜5社に見積もりを取りましょう。数が多すぎると管理が大変になるため、5社程度が理想的です。
- 大手業者(例:アート、サカイ、アリさんなど)
- 地元の中小業者(距離が近いほど安くなる傾向)
両方を混ぜて比較することで、最もコスパの良い業者を見つけられます。
3. 一括見積もりサイトを活用する
インターネット上の一括見積もりサービスを使えば、1回の入力で複数業者からの見積もりをまとめて受け取ることができます。
電話やメールが増えるデメリットはありますが、価格競争が起こりやすく、最も安くなる傾向があります。
4. 訪問見積もりを依頼する(荷物が多い場合)
単身引越しや荷物が少ない場合はオンライン見積もりで十分ですが、家族引越しや大型家具が多い場合は訪問見積もりが正確です。
訪問見積もりでは、
- 荷物の実際の量
- 階段や通路の広さ
- 搬入経路の確認
などを業者が直接確認してくれるため、後から追加料金が発生しにくくなります。
【相見積もりのコツと注意点】
1. 他社の見積もりを交渉材料に使う
最初に安い見積もりを提示してきた業者がいても、すぐに契約しないことが大切です。他社に「〇〇社はこの金額でした」と伝えることで、さらに値下げしてもらえるケースがあります。
- 具体的な金額を伝える(例:「他社では65,000円でした」)
- あくまで冷静に、強引な交渉は避ける
2. サービス内容も比較する
単に料金だけで選ぶのは危険です。見積もり書の中に以下のような項目が含まれているかをチェックしましょう。
- 段ボールやガムテープの無料提供
- 梱包・開梱サービスの有無
- 保険・補償内容
- エアコン・照明の脱着料金
一見安く見えても、オプション費用が高くつく業者もあります。
3. 即決を求められても焦らない
業者によっては「今決めていただければこの金額です」と即決を促すことがあります。その場で契約せず、一旦持ち帰って他社の見積もりと比較しましょう。焦って契約すると、後で後悔することが多いです。
4. 書面やメールで見積もりをもらう
口頭の見積もりはトラブルのもとです。必ず「見積書」を書面またはメールで受け取りましょう。金額・日時・オプション内容を明記してもらうことで、後の請求トラブルを防げます。
【相見積もりで得られるメリット】
- 業者間の競争で自然に値下げされる
- 料金の相場が把握できる
- 不当な追加料金を防げる
- 最もコスパの良いプランを選べる
相見積もりは「交渉のための材料を増やす」だけでなく、「安心して契約するための保険」としても非常に有効です。
引越し日を平日に設定する
引越し業者の料金は、基本的に「需要と供給」で決まります。
多くの人が休みを取りやすい土日祝日や月末、年度末(特に3月〜4月)は依頼が集中するため、料金が高騰します。
一方で、平日や月の中旬などの閑散日は依頼が少ないため、業者側も予約を埋めるために割安な料金を設定する傾向があります。
つまり、同じ距離・荷物量でも「いつ引っ越すか」によって、料金が大きく変わるのです。
【平日に引越すことで得られる主なメリット】
1. 費用が安くなる
業者の繁忙具合によりますが、平日を選ぶだけで20〜50%ほど安くなることも珍しくありません。
たとえば、土日が8万円の見積もりでも、平日なら6万円前後になるケースがあります。特に「火曜〜木曜」は予約が少なく、狙い目です。
2. 希望の時間帯を選びやすい
人気の「午前便」や「時間指定」は、土日だとすぐ埋まってしまいます。平日なら予約が取りやすく、希望通りのスケジュールを組みやすくなります。
・午前中に荷物を運び、午後から新居の整理ができる
・引越し先の立ち会いや電気・ガスの手続きも同日に済ませやすい
といったメリットもあります。
3. 渋滞や混雑が少なくスムーズに進む
平日は交通量が比較的少ないため、移動がスムーズです。トラックの遅延や駐車場所の確保がしやすく、結果的に作業時間の短縮につながります。
作業がスムーズに終わることで、業者側も追加料金を発生させずに済みます。
【平日に引越す際の注意点】
1. 仕事の休みを確保する
平日引越しの唯一のデメリットは、仕事や学校のスケジュール調整が必要になる点です。引越し日は1日休みを取るか、午後半休を活用するなど、事前に上司や学校に相談しておきましょう。
・有給休暇を利用する
・リモートワークの日に合わせる
・家族のうち1人が立ち会う
といった柔軟な方法で対応するのもおすすめです。
2. 手続き関係のスケジュールを確認する
役所での転出・転入届や、ガス・電気・水道の立ち会いなどは、平日しか対応していない場合があります。引越し当日や前後の日程を調整して、必要な手続きを効率よく済ませましょう。
- 役所の窓口:平日8:30〜17:00
- ガス開栓の立ち会い:平日対応が中心
これらを事前に確認しておくと、スムーズに引越しできます。
3. 予約は早めに行う
平日は比較的空いているとはいえ、年度末(3月)や大安日などは予約が集中します。安く引越すためには、1か月以上前に見積もりを取り、希望日の仮予約をしておくのが理想的です。
平日引越しが特におすすめの人
- 一人暮らしでスケジュールの自由度が高い人
- リモートワークやフリーランスで平日に動ける人
- 家族の中で誰か1人が立ち会える人
- 費用をできるだけ抑えたい人
これらに当てはまる人は、平日を選ぶことで確実にコストを下げられます。
平日でもさらに安くするための工夫
平日に加えて、以下の工夫を取り入れるとさらに節約効果が高まります。
- フリー便(時間おまかせ)を選ぶ
→ 業者が効率よく回れる時間に合わせるため、割安になる。 - 荷物を少なくしておく
→ 作業時間が短縮され、トラックのサイズも小さくできる。 - 早期予約割引を活用する
→ 1か月以上前の予約で特典を受けられることがある。
時間指定をしない
引越し料金は「作業の効率」で決まる部分も大きく、業者にとってスケジュールを自由に組める引越しは非常にありがたい案件です。
そのため、「時間指定をしない(フリー便)」にすると、業者側が他の引越しと同日にまとめて作業できるため、料金を割安に設定してくれることが多いのです。
つまり、「業者の都合に合わせる代わりに、安くしてもらう」という仕組みです。
時間帯別の料金傾向
一般的な引越しプランでは、以下のように時間帯ごとで料金が異なります。
| 時間帯 | 特徴 | 料金の傾向 |
|---|---|---|
| 午前便 | 人気が高く予約が集中する | 高い(基準価格) |
| 午後便 | 午前便の後に作業 | やや安い |
| フリー便(時間指定なし) | 業者の都合に合わせる | 最も安い |
特に「フリー便」は午前・午後のいずれになるか前日または当日に連絡がある形が多く、業者にとっても調整がしやすいため、料金が2〜3割ほど安くなる傾向があります。
フリー便(時間おまかせ便)の仕組み
「フリー便」または「時間指定なしプラン」は、次のような流れで行われます。
- 引越し日だけを決めて予約する
- 前日または当日に、業者から「午前・午後どちらの便になるか」の連絡がある
- 業者のスケジュール次第で時間が決定
引越し時間が確定するのがギリギリになる点はデメリットですが、その分、確実に費用を抑えられます。
フリー便が向いている人の特徴
- 引越し日には1日中立ち会える人
- 時間に余裕があり、細かいスケジュールに縛られない人
- とにかく費用を優先したい人
- 単身引越しや荷物が少ない人
上記に当てはまる場合、時間指定を外すだけで大きな節約になります。たとえば、午前指定が7万円のところ、フリー便なら5万円台で済むケースもあります。
【フリー便のメリット】
1. 料金が大幅に安くなる
他の引越しと同じトラックでまとめて回る「混載便」になることが多く、業者側のコストが下がるため、料金を安く提供できます。午前・午後指定を外すだけで、数千円〜1万円以上安くなることもあります。
2. スケジュール変更に柔軟
フリー便は、業者の作業順に合わせて柔軟に調整できるため、他の引越しが遅れても対応可能です。
結果として、キャンセルや追加費用のリスクも少なくなります。
【フリー便のデメリットと対策】
1. 開始時間が読めない
前日または当日に連絡があるため、予定を立てにくい点がデメリットです。
対応策としては、
- 当日は1日空けておく
- 午前・午後どちらにも対応できるよう準備を前日に完了しておく
- 重要な予定を別日にずらす
といった工夫をしておくと安心です。
2. 生活インフラの立ち会いと重なる可能性
電気・ガス・ネット回線などの立ち会いを同日に入れてしまうと、時間がかぶる可能性があります。
立ち会い系の作業は別日に分けて予約しておくとスムーズです。
午後便も費用を抑える選択肢
フリー便ほどではありませんが、「午後便」も料金がやや安くなる傾向があります。
午前の引越しが終わり次第作業に入るため、時間は多少前後しますが、「午前中は自分で荷造りをして、午後から引越し作業に立ち会う」という形も効率的です。
午後便は時間指定よりも自由度があり、かつフリー便よりも開始時間が予測しやすい中間的な選択肢です。
【フリー便を活用するコツ】
- 平日+フリー便を組み合わせると最も安くなる
- 繁忙期(3〜4月)を避けるとさらに割引率が上がる
- 見積もり時に「時間指定なしの場合いくら安くなりますか?」と聞く
この一言で、割引が適用されるケースが多いです。業者側もフリー便を好むため、快く対応してくれる場合がほとんどです。
荷物を減らす
引越し料金は大きく分けて以下の3つの要素で決まります。
- 荷物の量(トラックの大きさ・作業時間)
- 移動距離(運搬コスト・燃料費)
- 作業人数(人件費)
この中で最もコントロールしやすいのが「荷物の量」です。
荷物が少なければ、必要なトラックのサイズも小さくなり、作業員の人数や作業時間も減ります。つまり、荷物を減らす=引越し料金を直接下げることにつながるのです。
荷物を減らすことでどれくらい安くなるのか
引越し業者の料金体系は、トラックの大きさで区分されています。目安として、以下のような差があります。
| トラックの種類 | 荷物量の目安 | 平均料金(同一市内) |
|---|---|---|
| 軽トラック(単身) | 最小限の家具・段ボール10箱程度 | 約2〜3万円 |
| 2tトラック(単身〜2人) | 家電・衣類・家具中サイズ | 約5〜8万円 |
| 3tトラック(2〜3人) | 家具・家電が多い場合 | 約8〜12万円 |
| 4tトラック(家族) | 大型家具・複数の家電 | 約12〜20万円以上 |
荷物を減らして1サイズ小さいトラックで済むようにすれば、2〜5万円程度の節約が可能です。また、荷造りの手間も減り、梱包資材の費用も抑えられます。
荷物を減らすための実践ステップ
1. 現在の持ち物を「見える化」する
まず、今ある荷物を把握することから始めましょう。部屋ごとにリストアップすると、不要品が明確になります。
- 洋服 → 1年以上着ていないもの
- 家電 → 壊れている、または使っていないもの
- 本・雑誌 → もう読まないもの
- キッチン用品 → 同じ用途のものが複数あるもの
リスト化するだけでも、「これ要らないかも」と気づくものが多いはずです。
2. 「使っていない物」を基準に選別する
引越しは断捨離の絶好の機会です。迷ったときは、「直近1年で使ったかどうか」を判断基準にしましょう。
判断の目安:
- 半年以上使っていない → 処分候補
- 1年以上使っていない → 処分決定
sentimentalな理由で取っておいた物も、思い切って見直すことで荷物が大幅に減ります。
3. 不用品の処分方法を決める
不要な物を処分する方法は、目的によって使い分けるのがポイントです。
(1)売る:お金に変える
・メルカリ・ラクマなどのフリマアプリ
・リサイクルショップ
・家電買取サービス
→ まだ使えるものは「引越し費用の足し」にできる。
家電・家具は、早めに出品すれば高く売れやすいです。
(2)譲る・寄付する
・友人や家族に譲る
・自治体やボランティア団体に寄付する
→ 捨てるのはもったいない、誰かに使ってもらえる選択肢。
(3)捨てる:スッキリさせる
・自治体の粗大ごみ回収を利用
・不用品回収業者にまとめて依頼
→ 壊れている物や再利用できない物は早めに処分。
特に粗大ごみは予約制が多いため、引越し1〜2週間前には申し込みましょう。
4. 家具・家電は「新居に合うか」で判断する
引越し先の間取りや収納スペースによっては、今の家具が合わない場合もあります。サイズを確認し、合わないものは思い切って処分・買い替えを検討しましょう。
- 大型ソファ → 新居が狭くて入らない
- 洗濯機 → ベランダ設置不可のマンション
- カーテン → 窓サイズが違う
無理に持って行くと、結果的に「運搬費+買い替え費」が余計にかかることもあります。
5. 梱包前に「捨てる」「残す」を徹底的に分ける
荷造りを始める前に、荷物を次の3つに分類しておくと整理が早く進みます。
- 今後も使う → 残す
- 売る・譲る → 段ボールを分けておく
- 捨てる → ゴミ袋へ即分別
引越し直前になると時間がなくなりがちなので、1か月前から少しずつ処分していくのが理想です。
【荷物を減らすメリットは費用以外にもある】
荷物を減らすことで得られる効果は、単なる節約だけではありません。
- 荷造り・荷解きの時間が短縮される
- 新居がスッキリして整理しやすい
- 探し物が減る・生活がシンプルになる
- 片付けのストレスが減る
つまり、「引越しの節約」と「新しい生活の質向上」を同時に実現できます。
梱包を自分で行う
引越し料金の中には「作業費用」として、荷物の梱包・運搬・荷解きの手間賃が含まれています。そのうち、「梱包作業」は人件費が最もかかる部分の一つです。
業者の「おまかせプラン」を選ぶと、スタッフがすべての荷物を丁寧に箱詰めしてくれますが、1回あたり1万円〜3万円程度の追加料金が発生します。
つまり、自分で梱包を行えば、その分の人件費をまるごと節約できるのです。
梱包方法別の料金差
引越しプランによって、料金には明確な差があります。
| プラン名 | 内容 | 費用の目安(単身) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| おまかせプラン | 梱包〜開梱まで全て業者が実施 | 約8〜10万円 | 手間はないが高額 |
| ハーフプラン | 家具・家電のみ業者が梱包 | 約6〜8万円 | 部分的に節約可能 |
| セルフプラン | すべて自分で梱包 | 約4〜6万円 | 最も安い |
梱包を自分で行うだけで、2〜4万円の節約が可能になるケースが多く見られます。
【自分で梱包を行うメリット】
- 引越し料金を大幅に節約できる
自分で作業する分、人件費が不要になり、費用を抑えられます。 - 荷物の中身を把握できる
自分で詰めることで、どこに何があるかを明確に把握でき、引越し後の開梱がスムーズです。 - プライバシーを守れる
人に見られたくない私物や貴重品も自分で管理できるため安心です。 - 不要品を見直すきっかけになる
梱包しながら「これは本当に必要か」を見直せるため、自然と荷物整理が進みます。
梱包資材を上手に入手する方法
業者から段ボールやガムテープが無料でもらえる場合があります。見積もり時に必ず確認しましょう。
その他、無料または格安で手に入れる方法もあります。
- スーパー・ドラッグストア
→ 商品搬入後の空き段ボールを無料で譲ってもらえる。 - 家電量販店・ホームセンター
→ 大型のしっかりした箱が手に入りやすい。 - ネット通販(Amazon・楽天など)
→ 小物用・衣類用などサイズ別に購入できる。
梱包資材の目安(単身者の場合)
- 段ボール:20〜30箱
- ガムテープ:2〜3本
- 緩衝材(新聞紙・プチプチなど):適量
梱包を効率的に行う手順
1. 使わない物から順に詰める
いきなり生活必需品を箱詰めすると不便になります。まずは、季節外の服・本・趣味用品など、すぐ使わない物から始めましょう。
段階的に進めるのがコツです。
- 引越し1〜2週間前:使用頻度の低いものを梱包
- 引越し前日:日用品・寝具を梱包
- 当日:最後まで使うもの(歯ブラシ・着替えなど)をまとめる
2. 箱には「中身」と「部屋名」を明記
開梱時にどの部屋に運ぶか分かるように、箱の側面に中身と設置先の部屋名を書きましょう。
- 「食器(キッチン)」
- 「衣類(寝室)」
- 「書籍(リビング)」
これだけで、搬入時に業者が正しい場所に運んでくれるため、後片付けが圧倒的に楽になります。
3. 壊れやすい物は二重包装で保護
食器やガラス製品などは、1枚ずつ新聞紙やプチプチで包み、箱の底と隙間に緩衝材を入れます。
特に、重い食器類は段ボールの下段にまとめ、軽い物を上に詰めるのが鉄則です。
- グラス → プチプチ+新聞紙
- 皿 → 立てて入れると割れにくい
- 家電 → 元箱があれば再利用する
4. 重い物と軽い物は分けて梱包
重い物(本・食器など)と軽い物(衣類・タオルなど)を一緒に入れると、持ち運びにくくなります。
1箱の重さは15kg以下を目安にしましょう。
特に本は詰めすぎ注意。半分ほど入れたら、残りを軽い物で調整します。
5. 引越し当日に使う「手荷物」は別にまとめる
引越し直後に必要な物(貴重品・着替え・充電器・洗面道具など)は、1つのバッグにまとめて持ち運びましょう。これをしておくと、段ボールを開けずにすぐ生活を始められます。
【梱包を自分で行う際の注意点】
- 梱包が終わるまでに余裕を持つ
前日に慌てて詰めると、分類が乱れて開梱が大変になります。 - 危険物・貴重品は業者に任せない
現金・通帳・パソコンなどは必ず自分で管理する。 - 家具・家電の分解は慎重に
ねじ類を小袋にまとめて貼り付けるなど、再組み立てを意識する。
梱包を自分で行うときのスケジュール例(単身者向け)
| 時期 | 作業内容 |
|---|---|
| 引越し2週間前 | 不要品を処分・売却開始 |
| 引越し1週間前 | 衣類・書籍・小物を梱包 |
| 引越し3日前 | 食器・日用品を詰める |
| 引越し前日 | 当日使う物以外すべて梱包 |
| 当日 | 貴重品・身の回り品を手荷物にまとめる |
スケジュールを立てて少しずつ進めれば、無理なく完了します。
家電の取り外しを自分で行う
引越しの見積もりには、運搬費だけでなく、家電の取り外しや設置に関する作業費も含まれています。
特にエアコン・洗濯機・照明などは、専門的な作業が必要とされるため、業者に依頼すると1台あたり5,000〜15,000円程度の追加料金が発生します。
つまり、自分で取り外し・準備ができる家電については、事前に対応しておくだけで数千円〜数万円の節約が可能になります。
家電の取り外しで費用が発生する主な項目
引越し業者のオプションサービスとして代表的なのが以下の作業です。
| 家電の種類 | 業者作業内容 | 相場費用(1台あたり) |
|---|---|---|
| エアコン | 取り外し・取り付け(配管・ガス抜き含む) | 10,000〜20,000円 |
| 洗濯機 | 給水ホース・排水ホースの取り外し・設置 | 3,000〜8,000円 |
| 照明器具 | 天井への取り外し・取り付け | 1,000〜3,000円 |
| テレビ・レコーダー | 配線の抜き取り・再接続 | 2,000〜5,000円 |
| 冷蔵庫 | 運搬前の霜取り・水抜き | 無料(自分で可能) |
これらのうち、エアコン以外は自分で対応可能なケースが多いです。
自分で取り外しできる家電と注意点
1. 洗濯機
自分で行う人が最も多い家電です。作業手順は簡単で、ドライバーやタオルがあれば対応できます。
- 水道の元栓を閉める
- 給水ホースを外す(少量の水が出るためタオルを準備)
- 排水ホースを抜く
- 水滴を拭き取り、ホースをまとめて洗濯機にテープで固定
- ドラム式の場合は、輸送用ボルトを忘れずに取り付け
注意点:
- ドラム式洗濯機は輸送中の故障を防ぐため、必ず輸送固定ボルトを使用する
- 水漏れやホースの破損に注意する
2. 照明器具
天井に取り付けられている照明は、自分で簡単に外せます。
特別な工具は不要です。
- 電源を切る(ブレーカーを落とすと安全)
- シェードを外す(落とさないよう注意)
- プラグを回してソケットから外す
- 緩衝材に包んで箱に収納
注意点:
- 天井から外す際に脚立や椅子を使用する場合は転倒に注意
- シーリングタイプの場合、部品を失くさないように小袋で保管
3. 冷蔵庫
業者に頼むと「霜取り・水抜き」で追加費用がかかることがあります。
これは自分で簡単にできます。
- 引越しの前日までに電源を抜く
- 冷凍庫の霜を完全に溶かす(タオルで水を吸収)
- 内部を乾燥させる(カビ防止のため)
- 水受けトレイ(排水皿)を拭き取る
注意点:
- 電源を抜いてから24時間以上放置するのが理想
- 再設置時も電源はすぐ入れず、2〜3時間置いてから使用開始
4. テレビ・オーディオ機器
配線が複雑に見えますが、1本ずつ順に外せば難しくありません。
- 電源コードを抜く
- HDMIケーブル、アンテナ線、スピーカー線などを順に外す
- 配線の位置をスマホで撮影しておく(再設置が簡単)
- 緩衝材で包み、画面面を上にして運搬用箱へ
注意点:
- ケーブルをまとめてテープで固定しておくと紛失防止になる
- 大型テレビは2人以上で作業する
【エアコン取り外しは要注意】
エアコンは構造が複雑で、冷媒ガスを適切に処理しないと故障やガス漏れの原因になります。そのため、エアコンだけはプロに依頼するのが安全です。
業者に頼む際は、以下のように確認しましょう。
- 「取り外しのみ」なら5,000〜8,000円程度
- 「取り付け込み」なら10,000〜20,000円程度
- 複数台ある場合は割引が可能
※自分で取り外すと保証が効かなくなる場合もあるため注意が必要です。
【家電の取り外しで節約するコツ】
- できるものは自分で対応し、難しいものは専門業者に依頼する
- 見積もり時に「取り外しは自分で行う予定」と伝える
- 業者に頼む際は、まとめ依頼で割引交渉をする
- 照明・洗濯機・冷蔵庫は必ず「事前準備」をしておく
家電取り外しの準備スケジュール例
| 時期 | 作業内容 |
|---|---|
| 引越し3日前 | 冷蔵庫の霜取り開始 |
| 引越し2日前 | 洗濯機のホース取り外し・乾燥 |
| 引越し前日 | 照明器具の取り外し・配線確認 |
| 引越し当日 | 最終チェック・家電の運搬準備 |
計画的に進めれば、慌てず安全に作業ができます。
繁忙期を避ける
引越し料金は、荷物の量や距離だけでなく、引越しを行う時期(タイミング)によって大きく変動します。
引越し業界には明確な「繁忙期」と「閑散期」があり、需要の集中する時期には料金が高騰します。
需要が高い時期には、業者のトラックやスタッフの数が不足するため、同じ条件でも1.5〜2倍以上の料金差が出ることも珍しくありません。
そのため、スケジュールに余裕がある人ほど、繁忙期を避けるだけで大幅な節約が可能です。
引越しの繁忙期はいつ?
日本における引越し繁忙期は、以下のように明確に分かれています。
| 時期 | 状況 | 特徴 |
|---|---|---|
| 3月〜4月上旬 | 超繁忙期 | 新入学・転勤・就職などで依頼が集中 |
| 7月〜8月 | 準繁忙期 | 夏休みやお盆前の引越しが増加 |
| 9月末〜10月初旬 | 転勤シーズン | 企業異動で依頼が増える |
このうち、3月〜4月上旬は最も高騰する時期で、通常期と比べて2倍近くの料金になることがあります。
閑散期(おすすめの時期)はいつ?
逆に、業者の予約が取りやすく料金も下がる「閑散期」は以下の通りです。
| 時期 | 特徴 | 平均割引率(繁忙期比) |
|---|---|---|
| 5月〜6月 | 新生活後で需要が落ち着く | 約20〜40%安い |
| 9月中旬 | 夏の繁忙期が終わり余裕がある | 約15〜30%安い |
| 11月〜2月 | 年末年始以外は依頼が少ない | 約30〜50%安い |
特におすすめは、5月中旬〜6月末および11月〜2月の冬季期間です。この時期は業者が比較的暇になり、見積もり時の値下げ交渉がしやすいのも大きなメリットです。
繁忙期と閑散期の料金比較(例)
| 引越し時期 | 単身引越し | 家族引越し(3LDK) |
|---|---|---|
| 3月下旬(土日) | 約8〜12万円 | 約18〜30万円 |
| 6月中旬(平日) | 約4〜6万円 | 約10〜15万円 |
| 11月(平日) | 約3〜5万円 | 約8〜12万円 |
同じ距離・荷物量でも、時期をずらすだけで半額近くになるケースもあります。
なぜ3〜4月は高くなるのか(理由)
- 新入学・就職・転勤シーズン
進学・入社・異動などで全国的に引越しが集中。 - トラック・作業員不足
繁忙期は業者のリソースが限られるため、価格が上がる。 - 希望日・時間帯の競争が激化
土日・午前便はすぐに埋まり、割高になる。
繁忙期は「需要が集中し、供給が追いつかない」ため、どの業者も価格を下げる理由がなくなるのです。
繁忙期にどうしても引越す場合の対策
どうしても3〜4月の引越しが避けられない場合でも、以下の工夫で費用を抑えられます。
- 平日・午後便・フリー便を選ぶ
→ 午前便より2〜3割安い。 - できるだけ早く予約する(1〜2か月前)
→ 早期割引や希望日の確保が可能。 - 荷物を減らしてトラックのサイズを小さくする
→ 費用を圧縮できる。 - 見積もりは5社以上比較する
→ 繁忙期でも業者間で価格差がある。 - 引越し日をずらす(前倒し・後ろ倒し)
→ 月末や週末を避けると安くなる。
これらを組み合わせれば、繁忙期でも無理のない費用で引越しができます。
【繁忙期を避けるメリット】
- 引越し料金が安くなる(最大50%以上)
- 希望日時を選びやすい
- スタッフの質が安定している(余裕がある時期)
- 荷扱いが丁寧でトラブルが少ない
- 値下げ交渉がしやすい
繁忙期は作業員も多忙で疲労しているため、対応の質が下がることがあります。閑散期のほうが時間に余裕があり、丁寧に作業してもらえるという点でもおすすめです。
【引越し時期を決める際のポイント】
- 可能なら「月の中旬・平日」を選ぶ
月末・月初は契約更新や転勤が集中しやすい。 - カレンダーで大安や連休を避ける
縁起の良い日は予約が殺到して高くなる傾向。 - 会社の転勤時期に合わせる場合は早めに相談
社内規定の範囲で日程を調整できることもある。
梱包資材をリサイクルする
引越しの準備では、段ボール・ガムテープ・緩衝材などの梱包資材が欠かせません。
しかし、これらをすべて新品で購入すると、数千円〜1万円前後の出費になることがあります。
- 段ボール:1箱あたり100〜200円
- ガムテープ:1巻200〜300円
- プチプチ(緩衝材):10mで500〜1,000円
荷物量が多いほど必要数も増えるため、意外と馬鹿にならないコストです。
一方で、これらの資材は「再利用」できるものが多く、リサイクルを活用すれば、コストをほぼゼロに抑えることが可能です。
無料または格安で梱包資材を入手する方法
1. スーパー・ドラッグストアで段ボールをもらう
最も一般的で手軽な方法です。多くのスーパーでは、商品陳列後の空き段ボールを店頭にまとめて置いており、自由に持ち帰ることができます。
- 野菜や果物用の箱は丈夫で重い荷物に向いている
- お菓子・日用品用の箱は軽量で扱いやすい
- 持ち帰る際は、汚れや破れがないものを選ぶ
※スーパーによっては店員に声をかける必要がある場合もあります。
2. 家電量販店・ホームセンターを活用する
家電を搬入した際に使用した段ボールはサイズが大きく、厚みがあるため家具や大型品の梱包に最適です。
店舗で不要な箱をもらえる場合もあります。
おすすめの使い方:
- 掃除機・炊飯器などの箱 → 小型家電用
- テレビ・モニターの箱 → 衝撃保護に優れる
- 家電量販店で引き取ってもらった際の箱 → 再利用可能
3. 引越し業者から無料提供を受ける
多くの業者では、契約者に対して無料で段ボールを配布しています。
平均的には「単身引越しで10〜20箱」「家族引越しで30〜50箱」が目安です。
さらに、引越し後に使い終えた段ボールを無料で回収してくれる業者もあります。
見積もり時に「無料資材の提供・回収サービスの有無」を確認しておくとよいでしょう。
4. フリマアプリ・地域掲示板を利用する
最近では、フリマアプリ(メルカリ・ジモティーなど)で
「引越しで使った段ボールを無料で譲ります」といった投稿も多く見られます。
- 近隣エリアで受け取り可
- まとめて無料または100円〜200円程度で入手できる
- 使用済みでも清潔なものが多い
特に「引越しが終わったばかりの人」から譲り受けると、ちょうど良いサイズが揃いやすいです。
自宅でリサイクルできる梱包資材
1. 新聞紙・チラシ
プチプチの代わりに、新聞紙やチラシを丸めて詰めれば十分な緩衝材になります。
食器・コップなどの間に詰めるだけで、割れ防止効果が高まります。
コツ:
- 破れにくい紙を使用する
- グラスや皿は1枚ずつ包む
- 段ボールの隙間にも詰めて固定
2. 衣類やタオル
柔らかい素材の服・タオルを緩衝材代わりにすることで、
荷物が少なくなり、梱包資材の節約にもなります。
- コップや花瓶 → Tシャツ・タオルで包む
- 食器類 → 薄手の布で包んでまとめる
- 電子機器 → スウェットや毛布で保護
「緩衝材を買わずに済む」+「衣類を効率よく詰められる」一石二鳥の方法です。
3. ゴミ袋・レジ袋
軽いクッション代わりに使えるうえ、防水性もあるため便利です。特にキッチン用品や浴室用品など、水回りの小物をまとめる際に役立ちます。
梱包資材の再利用方法
引越し後も、使った段ボールや緩衝材を再利用することで無駄を減らせます。
- 段ボール → ごみ分別箱や収納ボックスに再利用
- プチプチ → 家電・家具の保護材として再使用
- ガムテープ芯 → ケーブル巻きなどに活用
さらに、業者が「資材回収サービス」を提供している場合は、不要な段ボールをまとめて無料で引き取ってもらえます。
【梱包資材をリサイクルする際の注意点】
- 汚れや湿気のある箱は使用しない
破れやすく、中身を傷つける原因になります。 - 底の補強を忘れずに
中古段ボールは強度が落ちているため、ガムテープを十字に貼って補強。 - サイズを統一して積みやすくする
形がバラバラだと運搬時に崩れやすくなるため、サイズを3〜4種類に絞ると効率的です。 - 再利用品は衛生状態を確認
食品や生鮮品を入れていた箱は、においやカビの原因になるため避けましょう。
【梱包資材をリサイクルするメリット】
- 新品資材を買う必要がなくコスト削減(最大1万円節約)
- 環境に優しい(エコ活動の一環)
- 近所・地域との交流のきっかけになる(譲り合い文化)
- 梱包作業に使える資材を確保しやすい
特に、引越し準備に余裕がある人は「早めに資材を集めておく」ことで、当日になって資材が足りないというトラブルも防げます。
キャンペーンや割引を活用する
引越し料金は、同じ条件でも業者によって大きく異なります。しかし、「見積もりを取るだけ」で適用できる割引サービスやキャンペーンが多く存在します。
これらを上手に利用することで、通常よりも1万円〜3万円以上安くなるケースも珍しくありません。
また、時期や申込方法によってはキャッシュバックや無料オプションが付くこともあり、「賢く選ぶだけで得をする」節約方法です。
主な引越し業者の割引・キャンペーン例
| 割引・特典の種類 | 内容 | 割引率・特典の目安 |
|---|---|---|
| 早期予約割引 | 1か月以上前に予約で割引 | 5〜20%OFF |
| WEB申込割引 | ネットから見積もり・契約した場合 | 1,000〜5,000円割引 |
| 平日割引 | 土日より平日に引越す場合 | 約10〜30%OFF |
| 学生・新社会人割 | 学生証・社員証の提示で適用 | 3,000〜10,000円引き |
| シニア割 | 60歳以上の利用者対象 | 5〜10%OFF |
| 複数台割引 | 家族や友人と同日に依頼 | 5〜15%OFF |
| キャッシュバックキャンペーン | 一括見積もりサイト経由など | 最大10,000円還元 |
| 不用品引取無料 | 指定品目に限り処分費が無料 | 家具・家電1点程度無料 |
| 段ボール無料提供 | 契約者に段ボール配布 | 10〜50箱無料 |
業者によって内容や時期は異なりますが、どの引越し会社も「新規顧客獲得」のためにお得な特典を用意しているのが現状です。
割引やキャンペーンを活用するコツ
1. 一括見積もりサイトを経由する
インターネット上の引越し一括見積もりサイトを利用すると、複数の業者から自動的に見積もりが届きます。
この方法を使うと、サイト限定の「キャッシュバック」や「特別割引」が適用されることが多いです。
メリット:
- 複数社の価格比較が簡単
- 通常より安い「WEB限定価格」になる
- キャンペーンコードを自動適用してくれる場合もある
注意点
- 見積もり後に営業電話が増えることがあるため、メール連絡希望を設定しておくと安心。
2. 早めに予約する
引越し業界は繁忙期になるほど値上がりする仕組みのため、予約が早いほど安くなります。
多くの業者では、「1〜2か月前の予約」で5〜20%の早割が適用されるケースがあります。
- 2か月前 → 最大20%OFF
- 1か月前 → 約10%OFF
- 直前予約 → 通常料金または割増
早めにスケジュールを決めておくことが、確実な節約につながります。
3. 平日・午後便を選ぶ
ほとんどの業者が、平日・午後便・フリー便(時間指定なし)に対して割引を設定しています。
これは、業者側のスケジュール調整がしやすくなるためです。
活用のコツ:
- 平日+午後便を選ぶと最大30%割引になる場合も
- 予約時に「時間おまかせで安くできますか?」と聞くだけで値下げされることもある
4. 不用品引取キャンペーンを活用する
多くの業者が、引越し時に出る不要家具や家電を「無料または割引価格」で引き取ってくれます。
処分業者に頼むと数千円かかるため、非常にお得です。
- テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど
- テーブル、椅子、収納棚
注意点
- 破損が激しいものや古い家電は対象外になる場合もあるため、事前確認を。
5. WEB限定キャンペーンを見逃さない
公式サイトから直接申し込むことで、限定の特典が受けられるケースもあります。
例えば以下のようなものがあります。
- 見積もり依頼だけでクオカード・電子マネーがもらえる
- WEB限定で段ボールやガムテープを無料提供
- 契約時にAmazonギフト券プレゼント
定期的に内容が変わるため、申し込み前に公式サイトを確認しておくのがおすすめです。
6. 学生・シニアなどの「属性割引」を使う
引越し業者の中には、特定の利用者層向けに「属性割引」を設けているところもあります。
- 学生割:卒業・入学シーズンの単身引越し向けプラン(書類提示で適用)
- シニア割:60歳以上で5〜10%OFF、作業補助付きの特別プランもあり
自分の条件に合う割引があるかを見積もり時に確認するだけで、簡単に利用できます。
7. 複数台・同日割引を狙う
家族・知人と同じ日に引越しをする場合、同日割引を利用できる業者もあります。
トラックを効率的に使えるため、1台あたりのコストが下がるのです。
- 同じマンション・同じエリアで複数人が依頼
- 家族の引越しをまとめて申し込む
見積もり時に「同日に複数台依頼する予定です」と伝えるだけで値引きされることがあります。
【キャンペーンを利用する際の注意点】
- キャンペーンの適用条件を確認する
期限や対象地域、支払い方法などが限定されていることがあります。 - 他の割引との併用可否をチェック
「早割」と「WEB割」が併用できないケースもあるため、確認が必要です。 - キャンペーン期間を逃さない
多くは季節限定(春・秋)で行われるため、早めの情報収集が重要です。 - 「安すぎる」業者には注意
極端に安い見積もりは後から追加料金が発生する可能性もあるため、内訳を必ず確認。
【キャンペーン活用で得られるメリット】
- 同じサービス内容でも1〜3万円安くなる
- 段ボール・緩衝材が無料になる
- 不用品処分費が浮く
- ギフト券やポイント還元が受け取れる
- 費用を抑えながら満足度の高い引越しができる
オプションサービスを見直す
引越しの見積もりには、基本料金(運搬費・人件費・車両費など)に加えて、オプションサービス費用が上乗せされていることが多くあります。
便利なサービスが多い反面、実際には「使わなくても済む内容」や「自分でできる作業」も多いため、不要なオプションを外すだけで数千円〜数万円の節約につながります。
つまり、オプションの見直しは「品質を下げずに引越し費用を下げる」最も確実な方法です。
引越し業者の主なオプションサービス一覧
| サービス内容 | 概要 | 費用の目安 | 自分で代替可能か |
|---|---|---|---|
| 梱包サービス | 荷物の箱詰め〜開梱を代行 | 10,000〜30,000円 | 〇 |
| エアコン脱着 | 取り外し・取り付け | 10,000〜20,000円 | △(一部可) |
| 洗濯機設置 | ホース接続・動作確認 | 3,000〜8,000円 | 〇(説明書で可) |
| 照明取り外し | 天井から外す作業 | 1,000〜3,000円 | 〇 |
| テレビ・配線接続 | AV機器の再接続 | 2,000〜5,000円 | 〇(写真を撮っておけば可) |
| ハウスクリーニング | 退去時の清掃代行 | 10,000〜30,000円 | △(掃除で代用可) |
| 不用品回収 | 家具・家電の処分 | 0〜10,000円 | △(自治体回収可) |
| ピアノ・金庫運搬 | 特殊運搬 | 15,000〜40,000円 | ✕(専門業者必要) |
この表の通り、実際に自分で対応できる作業が多いことがわかります。
【オプションを見直すメリット】
- 引越し料金の無駄を省ける
必要最低限のサービスに絞ることで、費用がスリムになる。 - 自分のペースで準備できる
梱包や取り外しを自分で行うと、慌てずに計画的に作業可能。 - トラブルを防げる
他人に任せる範囲を減らすことで、破損や紛失のリスクを下げられる。
よくある「不要になりがちな」オプション例と見直し方法
1. 梱包サービス
「おまかせパック」など、荷造りをすべて業者に任せるプランは便利ですが高額です。
段ボールやガムテープは無料提供されることが多いため、自分で梱包すれば2〜4万円の節約になります。
- 壊れやすいものだけを業者に任せる「部分おまかせ」を選ぶ
- 本や衣類など、自分で簡単に詰められるものは自分で
2. エアコン・照明の取り外し
エアコン取り外しは専門業者が必要ですが、照明器具や小型家電は自分で外せます。
- 業者依頼 → 1台あたり5,000〜10,000円
- 自分で対応 → 無料(ドライバー1本で可能)
※エアコンのみはプロ依頼を推奨(冷媒ガス処理が必要なため)
3. 不用品回収サービス
引越し業者に依頼すると、処分費用が高くなる傾向があります。
一方、自治体の粗大ごみ回収やリサイクルショップを使えば格安または無料です。
- 自治体の粗大ごみ受付 → 1品300〜1,000円程度
- メルカリ・ジモティーなど → 売却または無料譲渡
- リサイクルショップ → 家電・家具を買い取ってもらえる
4. ハウスクリーニング
退去時の掃除を業者に頼むと、1DKで10,000円以上かかることもあります。
しかし、賃貸の場合は原状回復クリーニングを管理会社が実施するため、
自分で軽く掃除しておくだけで十分なケースもあります。
- 床・水回り・壁の汚れを落とす程度でOK
- 掃除用具は100円ショップで揃う
5. テレビやネットの配線設定
業者の配線サービスは意外と高額です。
しかし、最近のテレビやルーターは設定が簡単で、説明書やメーカーサイトを見れば自力で可能です。
- 引越し前に「配線状態をスマホで撮影」
- 接続の順番をメモしておく
- 必要なら再設定ガイドを印刷しておく
【見直し時に注意したいポイント】
- 契約前にオプションの一覧を確認する
見積もり書にはオプションが自動的に含まれていることが多いです。
不要な項目を削除してもらいましょう。 - オプションの「一部利用」も可能
全部外すのではなく、必要なものだけ選択(例:エアコンのみ依頼)。 - オプション費用の相場を把握する
相場より高い場合は、他社に見積もりを取ることで交渉材料になります。 - 「無料サービス」との違いを理解する
無料の段ボール提供などと混同しないよう、付帯費用を確認。
見直しの手順
-
見積もり書をよく確認する
「基本料金」と「オプション料金」を分けて見る。
-
不要な項目に×印をつける
「梱包サービス」「不用品回収」など削除候補を明確に。
-
業者に再見積もりを依頼する
不要オプションを外した金額を提示してもらう。
-
複数社で比較する
オプション抜きの価格を比較すれば、より正確な相場がわかる。
【オプションを見直すことで得られる効果】
- 無駄な費用を1〜5万円削減できる
- 自分の手で管理でき、作業内容が明確になる
- トラブルの原因(破損・紛失)を減らせる
- 必要なサービスにだけお金をかけられる
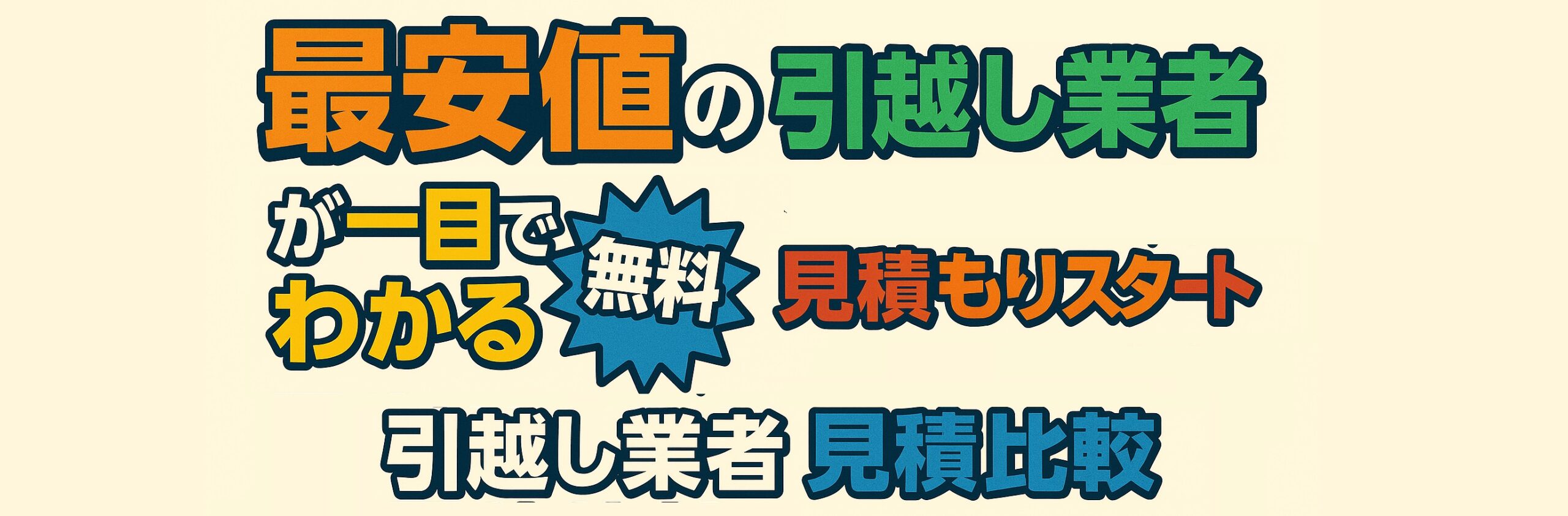
|

